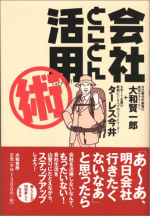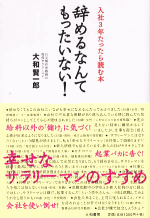2004/09/29(第83号)
*
───────────────────────────────────
■
■ 28〜30歳の若手社員が、初めて経験する「離」の時期
■
──────────────────────────────
⇒【前号までのあらすじ】自分が『何のために存在しているのか?』
に迷ったら、「社会とのつながり」を意識してみる。『会社に自分
の机があるから、会社に行く』。それだけでも、立派な存在意義である。
*
●こんにちは。ひと儲けドットコムの大和です。あなたは、小学生
の頃、良く晴れた日に、理科の授業で「虫めがねで紙を焦がす」と
いう実験をやった記憶はありませんか?
*
●直径5センチぐらいの、小さなレンズでも、簡単に紙を焦がすこ
とができる。上手くやれば、火をつけることも可能です。
●エネルギーを一点に集中する。コツは、いかにして、しっかりと
焦点を合わせるか? 焦点が定まったら、あとは、じっくり待つ。
レンズの大小よりも「一点集中力」が重要なんです。
*
●実は、私たちサラリーマンも含めて、一人の人間が持っているレ
ンズの大きさには、さほど違いはありません。
●あなたの10倍の年収を稼いでいる人が、必ずしも、あなたのレ
ンズより10倍大きなレンズを持っているわけではない。
*
●にも関わらず、多くの人は『まだ、自分のレンズの大きさが足り
ないから、火がつかないんだ!』と悩んでしまう。そして、レンズ
を巨大化するために、一生懸命頑張る。
●もちろん、レンズが大きければ有利であることは間違いないので
すが、最終的に、焦点が合っていなければ、いくら頑張っても、火
をつけることは難しい。
●そして、もっと大切なことは『どこに焦点を合わせたいのか?』
を、自分自身が、しっかりと決めているかどうか? なのです。
*
------------------------------------------------------------
従順だった部下が、ある日突然、牙をむく本当の理由とは?
------------------------------------------------------------
●では、焦点をしっかりと合わせるためには、具体的に、どうすれ
ばよいのか?
*
●例えば、あなたが、高速道路で車を運転する時、視点は、通常よ
りも遠くを見ているはずです。そのほうが、視野が安定して、焦点
を合わせることができる。
●つまり、焦点を合わせるために必要なことは、遠くを見ること、
すなわち「長期的な視野を持つこと」なのです。では、長期的な視野
を持つためには、どうすればいいのか?
*
●ところで、あなたは、「守」「破」「離」(しゅ・は・り)という
言葉を、聞いたことがありますか?
守(しゅ): 守る。 師の教えを、忠実に守る時期。
破(は): 破る。 師の教えを、意識的に破る時期。
離(り): 離れる。 師から離れて、独自の道を歩む時期。
*
●人が成長する過程では、守 → 破 → 離 という3つの段階があると
いう考え方。足利義光の時代に「能」の世界で生まれたと言われています。
●では、この考え方を、サラリーマンの人生に当てはめてみると、
どうなるか?
*
守 : 入社1〜3年目 守る。 上司の教えを、忠実に守る時期。
破 : 入社4〜6年目 破る。 上司の教えを、意識的に破る時期。
離 : 入社7〜9年目 離れる。 上司から離れて、独自の道を歩む時期。
*
●例えば、学卒22歳で入社した場合、守:22〜24歳、破:25〜27歳、
離:28〜30歳、という年代になります。私は現在、27歳ですから、
ちょうど、「破」から「離」に移行しつつある時期でしょう。
*
●そして、若手社員にとって、一番大切な時期は、「離」の時期、
つまり、28〜30歳の時期なのですが、この時期に、どのような
意思決定をするか? が、とても重要になってきます。
●なぜなら、単純に「離れる」と言っても、そこには、大きく分けて、
3つの意味が含まれているからです。その3つの選択肢のうち、どれを
選ぶのか? それを、冷静に見極めなければなりません。
*
------------------------------------------------------------
離れてみなければ、分からないこともある。
------------------------------------------------------------
●では、「離」に含まれる、3つの選択肢とは、具体的に、どのよ
うな内容なのか? 以下に挙げてみます。
1.会社から離れる(退職・独立)
2.上司から離れる(昇進・配置換え)
3.心だけが離れる(忠誠心の崩壊)
*
●まず、1.について。これは、会社を辞めて独立するとか、ある
いは、同業他社に転職するとか、いわゆる「退職」です。一番分か
りやすい「離」の典型ですね。
*
●次に、2.について。多くのサラリーマンは、30歳前後になると、
何らかの役職、具体的には「係長クラス」の地位が与えられるケース
が多いです。
●もしくは、別の部署に配置換えになって、心機一転、頑張ろう!
みたいなタイミングが、必ず訪れる。つまり、今までの上司から、
物理的に離れることができる、というわけです。
*
●そして、3.について。これは『その上司への忠誠心を、完全に
失っている状態』を意味します。尊敬できるところが1つも無い。
でも、給料を貰うために、仕方なく、従順なフリをしているだけ。
*
●このように、「離」の中には、上記のような、3つの選択肢があ
ります。これから選ぶ人も、すでに選んできた人も、上記のいずれ
かに、思い当たる節があるのではないでしょうか?
*
------------------------------------------------------------
長期的にサイクルを眺め、次のタイミングを見逃すな!
------------------------------------------------------------
●ここで、もう1つ、知っておくべきこと。それは「守・破・離」の
サイクルには、リピート性があるということ。つまり、繰り返すのです。
あなたが死ぬまで、永遠に。
*
●なぜなら、「離」の先には、必ず、次の「守」があるから。独立
したら、新たに目標とする人(師匠)が、必ず現われる。社内で配
置換えになったら、そこには、また新しい上司が存在する。
●ですから、もし、あなたが今、「離」の時期で、最適な選択肢を
選び損ねて、立ち往生していると感じても、まったく心配はいりません。
また、新しい「守」を見つければよいのですから。
*
●その「守」は、今の仕事に埋もれているかもしれないし、あなたの
上司にも、まだ残っているかもしれない。それは、決して無くなっ
てしまったわけではありません。ただ、見えていないだけなのです。
●新しい「守」の発見は、あなたの人生が、次のステップに進むための、
大きな掛け橋になります。「一皮向ける瞬間」と言ってもよいでしょう。
●今、あなたが勤めている会社の中で、新たな「守」を見つけるこ
とができたならば、そこには、まだまだ、スキルアップのチャンスが
あるということ。ですから、慌てて辞める必要は無いのです。
*
●ですが、いつまでも「守」の状態に留まっていては、文字通り
『保守的な人生』になってしまう。だから、やがてまた訪れるで
あろう、「破」と「離」の時期を、見逃してはいけません。
●次のサイクルは、あなた自身が、作っていくのです。あなたのサ
ラリーマン人生を、長期的な視野で、分析してみる。次の「破」そして
「離」は、いつ来るのか? そして、その時あなたは、何歳なのか?
*
●もし、その時期が明確に見えたとき、今までピンボケだった、あ
なたの焦点は、ピッタリと合うのです。そうなれば、もう、火がつ
くのは、時間の問題ですね。
(次号につづく…)
───────────────────────────────────
■
■ シリーズ企画: 絶対に損したくない!退職準備マニュアル【36】
■
──────────────────────────────
テーマ: 税金
サラリーマンの税金は、ガラス張りだから、損なのか?
*
●毎月の給与明細や、ボーナスの明細を見ると、たくさんの所得税や
住民税が、しっかり引かれていますよね? しかも、その税額が、
どのようなルールで計算されたのかさえ、よく分からない。
●それを見て『なんで、サラリーマンばっかり、無条件に、厳しく
取り立てられるんだ? 不公平だ!』と感じてる人も、いるかもし
れません。
*
●確かに、税務署から見れば、サラリーマンほど「税金を徴収しや
すい職業」はありません。その証拠に「トウゴウサンピン」という
言葉があります。
サラリーマン : 10割
自営業 : 5割
農家 : 3割
政治家 : 1割
*
●これは、税務署から見た『税金の補足率』を表す言葉です。つまり、
サラリーマンの税金は、源泉徴収で、給料から強制的に引かれますから、
ごまかしや、節税が効かないので、取りっぱぐれが無い、という意味。
●一方、自営業者や、個人事業主の場合は、交際費など、領収証を
しっかり取っておけば、経費として申告できるので、脱税にならない
範囲内で、しっかりと節税することが可能です。
*
●そう考えると、サラリーマンだけが、一方的に不利なように感じ
る人もいるでしょう。しかし、実際は、そうとも言い切れません。
その理由は、以下の3つです。
1.サラリーマンには「給与所得控除」が認められている
2.福利厚生など「会社のお金で○○できる!」という恩恵が受けられる
3.税務知識の習得、帳簿付け、申告作業などの業務から開放される
*
●まず、1.について。「給与所得控除」の概要については、前号で
もお伝えしましたが、ようするに、年収500万円のサラリーマンなら、
そのうち、154万円には、所得税がかからない、ということです。
*
●次に、2.について。通勤費の支給、寮や社宅の提供、健康診断、
各種手当など、会社のお金で『安く使える! タダで使える!』という
恩恵を受けている人は多いと思います。私も、その一人です。
●では、なぜ、このような恩恵が受けられるのか? それは、経営者
から見て「節税対策」になるからです。福利厚生費の多くは、会社の
経費として申告できますから、そのほうが、税金が安くなるのです。
●経営者からすれば『どうせ税金で取られるぐらいなら、福利厚生
という形にして、社員に還元したほうがいい』と考えるでしょうし、
実際に、税法も、その行為を推奨するようなルールになっています。
*
●もし、日本の税法が、サラリーマンに対して、圧倒的に不利な内容
だとしたら、それに気付いたサラリーマンたちは氾濫を起こし、学生
はみな、就職せずに、フリーランサーという雇用形態を望むでしょう。
●しかし、実際には『社員になれば、福利厚生が受けられる』という
メリットがあることを、誰もが知っている。そして、会社の福利厚生
を支えているのは、税法で認められている「節税対策」に他ならない。
*
●まさに、「飴とムチ」ですね。「福利厚生」という「飴」に、
「トウゴウサンピン」という「ムチ」。非常に上手いやり方です。
とてもバランスの良いルールだと、私は思います。
●ですから、私たちは、「ムチ」ばかりに目を奪われるのではなくて、
もっと「飴」に目を向けるべきなのです。だからこそ、会社の福利厚生は、
徹底的に使い倒さなければなりません。
*
●そして、3.について。私たちサラリーマンは、所得税と住民税だけ
を意識すればいいし、しかも、年末調整などの面倒な作業は、すべて
会社の経理部が代行してくれます。
●しかし、個人事業主になると、所得税や住民税はもちろん、事業税や
消費税まで考慮しなければならない。そして、それらに付随する帳簿付け
の作業や、申告作業なども、すべて自分の責任で実施する必要があります。
●もちろん、税理士を雇い、代行してもらえばよいのですが、それには
人件費もかかりますし、「良い税理士を選ぶ」のも、なかなか難しいの
が現状のようです。
*
●このように、税法は、非常にバランス良く作られているのですから、
サラリーマンだけが、一方的に不利だと考えるのではなく、サラリーマン
ならではの恩恵に目を向けて、それをしっかりと使い倒しましょう。
(次号につづく…)
*
|
このような内容のメールを、あなたのアドレス宛てに
無料でお届けします。
他のバックナンバーも読む
幸せなサラリーマンになる方法−気づきの視点と発想力
(マガジンID:0000127191)
登録は無料です。いつでも解除できます。↓↓↓
Powered by

|
大和賢一郎の著書
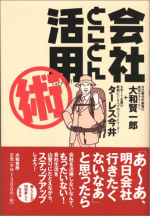
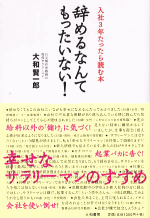
メールマガジン
幸せなサラリーマンになる方法−気づきの視点と発想力 (マガジンID:0000127191)
登録は無料です。
いつでも解除できます。
↓↓↓
Powered by

|